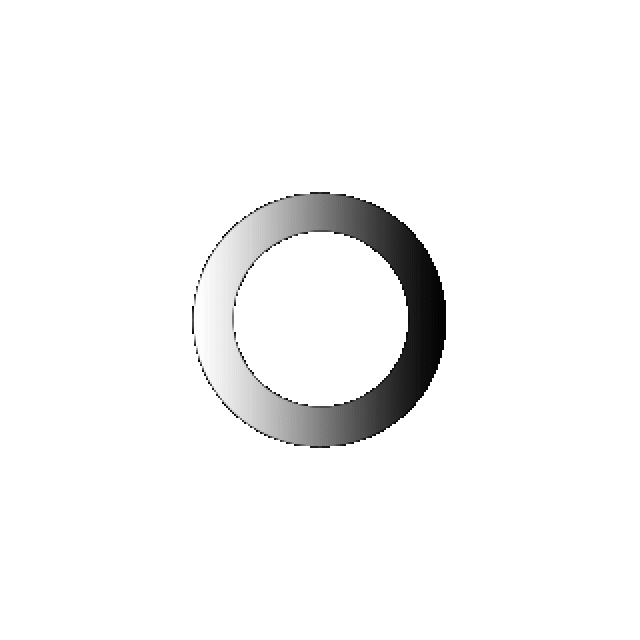ディレクターバブリアン作 短編小説 「 古くなったピアノ 」2
短編小説
続き→→
エミは白いお城がその中にそびえ立つ大きな大きな大きな門の前に立っていた。
人間の力はとてもとても開けられそうにない、巨大な門だ。
その門のちょうどエミの頭位の所にある、小さな小窓がパカっと空いて、
中から真っ黒い何かがこちらをジロリとのぞいてきた。
「エミちゃんですね。女王様から聞いています。ちょっとお待ちくださいね。」
とだけ言って、小窓がパコっとしまった。
閉まると同時に地響きがするようなギギギギギ~という音がして、少しづつ大きな扉が開いた。
扉の向こうからはどんどん明るい光が洩れて来て、眩しさに慣れた頃に、
エミの目に飛び込んできたのは、思わず声を出してしまうほどの光景だった。
黒いピアノ、白いピアノ、赤いピアノ、たくさんのピアノ達がお城の前のキレイな庭で、楽しそうにお話している。
よく見ると子供のピアノもいる。小さい子が弾く鍵盤の少ない小さなピアノだ。
自分の音色を自慢するものもいれば、ピアノの表面に描かれた柄を自慢するものもいて、
キレイなピアノの音が溢れ、音が様々な色になって空気中をふわふわ漂っていた。
エミはこんなにキレイな光景を見たことはなかった。
「エミちゃん、女王さまがお呼びです。私、ドミソがご案内しますよ。」
赤と黒のかっこいいピアノカバーで着飾ったオーソドックスタイプのピアノがエミに話かける。
エミは言われるままに、黒いオーソドックスタイプのピアノについていった。
お城の中に入ると、壁一面、高い天井にも楽譜が描かれていて、
お城の奥の方から聞いたこともないような滑らかで美しいピアノの音色が聞こえてきた。
その音色が七色になってフワフワをエミの体を包むと、音が聞こえてくるお城の奥へとエミを運んでいってくれた。
お城の一番奥は一面教会の様なステンドグラスにで囲まれていて、ステンドグラスにも楽譜が描かれていて、
聞こえてくる音色と共に、楽譜の音符達が踊る様に跳ねる。
その部屋の奥、丁度天井からキラキラした光が差し込む所に、美しい彫刻が施された真っ白なグランドピアノがいた。
ずっと聞こえていた音色はその白いグランドピアノから聞こえていた。
ゆっくり近づくと、音色がそっと止んだ。
「エミちゃん。はじめまして。今日は来てくれてありがとう。」
「は・・・はじめまして。あなたは?」
「私は、このピアノの国の女王のメロディです。」
「ピアノの国??」
「そうです、ここはピアノの国。
人間の世界にいるピアノ達は、ピアノを弾いてくれる人々が寝静まった頃、この故郷に帰って来たりしているのよ。」
「メロディ女王さま、私はなぜこの国にくることが出来たの?」
「エミちゃんは、私達の仲間、こげ茶色のピアノのファソラが他のピアノを同じように捨てられそうになったのを、
泣いてかばってくれたでしょ。それがみんなとても嬉しくてね。
人間がみんなエミちゃんのようだったらいいのに・・・ってね。
だから、せめてものお礼にこのピアノの国に招待することにしたの。」
「そうなんですね。・・・私のピアノ、ファソラっていうんですね。」
「ええ、そうよ。ファソラは仲間の中でもだいぶおじいさんなの。
今日は、お城の演奏会や、他のピアノ達とのたくさんお話して楽しんでね。」
エミはとりあえずお城の中を歩いてみることにした。
さっき案内してくれた黒いピアノのドミソが一緒についてきてくれるようだ。
長い廊下には、たくさんの音が色になっていて、とても愉快で気持ちよかった。
「ねえ、ドミソさん。あのピアノは何してるの?
「あのピアノは、今鍵盤を磨いてもらっているんだよ。鍵盤までキレイにしてくれる人間は少ないからね。」
「ふ~ん。じゃ、あの赤いピアノは?」
「赤いピアノは、油が足りなくなったから、油を付けてもらってるんだ。
人間が弾いた時に鍵盤が重く感じてしまわないようにね。」
ドミソはエミに得意げに色んなことを教えた。
お城を一回りして、庭に出てみる。
庭にある噴水の横に、小鳥がたくさん集まっていくのが見えた。
エミが近づいてみるとそこには、エミのこげ茶色のピアノ、ファソラがいた。
ファソラにはたくさんの小鳥が並んでとまり、ファソラが奏でる優しい音色に合わせて右に左に揺れている。
ファソラは嬉しそうに優しい表情で小鳥たちを見ていた。
エミはちょっとドキドキしながら、ファソラに近づいた。
まさか自分のピアノと話せる日が来るなんて思っていなかった。
「ファソラ、エミよ。」
「知ってるよ。女王がよんでくれたそうだね。」
「うん。」
「いつも大事に弾いてくれてありがとう。」
「うん。」
「君が2歳の時にイスによじ登って、私の鍵盤を弾いた時は本当に驚いたよ。」
「え?そうなの?」
「君のママが、ちょっと目を離したすきに、私によじ登ってね。
もう落ちるんじゃないか心配で心配で仕方なかったよ。
でもね、何とか登って鍵盤を触り始めたんだ。そっとね。」
「私、どんな顔してた?」
「それはそれは目をキラキラ輝かせていたよ。
その目を見た時にね、この子は私をきっと大事にしてくれると思ったんだ。」
「ふ~ん。」
続く→→
エミは白いお城がその中にそびえ立つ大きな大きな大きな門の前に立っていた。
人間の力はとてもとても開けられそうにない、巨大な門だ。
その門のちょうどエミの頭位の所にある、小さな小窓がパカっと空いて、
中から真っ黒い何かがこちらをジロリとのぞいてきた。
「エミちゃんですね。女王様から聞いています。ちょっとお待ちくださいね。」
とだけ言って、小窓がパコっとしまった。
閉まると同時に地響きがするようなギギギギギ~という音がして、少しづつ大きな扉が開いた。
扉の向こうからはどんどん明るい光が洩れて来て、眩しさに慣れた頃に、
エミの目に飛び込んできたのは、思わず声を出してしまうほどの光景だった。
黒いピアノ、白いピアノ、赤いピアノ、たくさんのピアノ達がお城の前のキレイな庭で、楽しそうにお話している。
よく見ると子供のピアノもいる。小さい子が弾く鍵盤の少ない小さなピアノだ。
自分の音色を自慢するものもいれば、ピアノの表面に描かれた柄を自慢するものもいて、
キレイなピアノの音が溢れ、音が様々な色になって空気中をふわふわ漂っていた。
エミはこんなにキレイな光景を見たことはなかった。
「エミちゃん、女王さまがお呼びです。私、ドミソがご案内しますよ。」
赤と黒のかっこいいピアノカバーで着飾ったオーソドックスタイプのピアノがエミに話かける。
エミは言われるままに、黒いオーソドックスタイプのピアノについていった。
お城の中に入ると、壁一面、高い天井にも楽譜が描かれていて、
お城の奥の方から聞いたこともないような滑らかで美しいピアノの音色が聞こえてきた。
その音色が七色になってフワフワをエミの体を包むと、音が聞こえてくるお城の奥へとエミを運んでいってくれた。
お城の一番奥は一面教会の様なステンドグラスにで囲まれていて、ステンドグラスにも楽譜が描かれていて、
聞こえてくる音色と共に、楽譜の音符達が踊る様に跳ねる。
その部屋の奥、丁度天井からキラキラした光が差し込む所に、美しい彫刻が施された真っ白なグランドピアノがいた。
ずっと聞こえていた音色はその白いグランドピアノから聞こえていた。
ゆっくり近づくと、音色がそっと止んだ。
「エミちゃん。はじめまして。今日は来てくれてありがとう。」
「は・・・はじめまして。あなたは?」
「私は、このピアノの国の女王のメロディです。」
「ピアノの国??」
「そうです、ここはピアノの国。
人間の世界にいるピアノ達は、ピアノを弾いてくれる人々が寝静まった頃、この故郷に帰って来たりしているのよ。」
「メロディ女王さま、私はなぜこの国にくることが出来たの?」
「エミちゃんは、私達の仲間、こげ茶色のピアノのファソラが他のピアノを同じように捨てられそうになったのを、
泣いてかばってくれたでしょ。それがみんなとても嬉しくてね。
人間がみんなエミちゃんのようだったらいいのに・・・ってね。
だから、せめてものお礼にこのピアノの国に招待することにしたの。」
「そうなんですね。・・・私のピアノ、ファソラっていうんですね。」
「ええ、そうよ。ファソラは仲間の中でもだいぶおじいさんなの。
今日は、お城の演奏会や、他のピアノ達とのたくさんお話して楽しんでね。」
エミはとりあえずお城の中を歩いてみることにした。
さっき案内してくれた黒いピアノのドミソが一緒についてきてくれるようだ。
長い廊下には、たくさんの音が色になっていて、とても愉快で気持ちよかった。
「ねえ、ドミソさん。あのピアノは何してるの?
「あのピアノは、今鍵盤を磨いてもらっているんだよ。鍵盤までキレイにしてくれる人間は少ないからね。」
「ふ~ん。じゃ、あの赤いピアノは?」
「赤いピアノは、油が足りなくなったから、油を付けてもらってるんだ。
人間が弾いた時に鍵盤が重く感じてしまわないようにね。」
ドミソはエミに得意げに色んなことを教えた。
お城を一回りして、庭に出てみる。
庭にある噴水の横に、小鳥がたくさん集まっていくのが見えた。
エミが近づいてみるとそこには、エミのこげ茶色のピアノ、ファソラがいた。
ファソラにはたくさんの小鳥が並んでとまり、ファソラが奏でる優しい音色に合わせて右に左に揺れている。
ファソラは嬉しそうに優しい表情で小鳥たちを見ていた。
エミはちょっとドキドキしながら、ファソラに近づいた。
まさか自分のピアノと話せる日が来るなんて思っていなかった。
「ファソラ、エミよ。」
「知ってるよ。女王がよんでくれたそうだね。」
「うん。」
「いつも大事に弾いてくれてありがとう。」
「うん。」
「君が2歳の時にイスによじ登って、私の鍵盤を弾いた時は本当に驚いたよ。」
「え?そうなの?」
「君のママが、ちょっと目を離したすきに、私によじ登ってね。
もう落ちるんじゃないか心配で心配で仕方なかったよ。
でもね、何とか登って鍵盤を触り始めたんだ。そっとね。」
「私、どんな顔してた?」
「それはそれは目をキラキラ輝かせていたよ。
その目を見た時にね、この子は私をきっと大事にしてくれると思ったんだ。」
「ふ~ん。」
続く→→