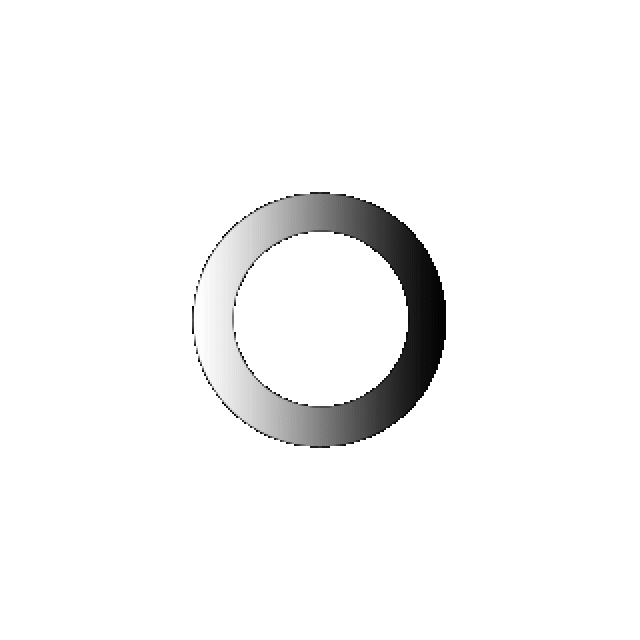ディレクターバブリアン作 短編小説 「 バナナは僕のガードマン 」2
短編小説
続き→→
僕は、いつもより30分も早く教室についた。
僕の反撃開始の記念すべき日だからだ。
準備OK、僕は今日から最強になれる!僕にはヤツがいる!
クラスのみんなが教室に着き始め、ランドセルから筆記用具、教科書、ノート・・・と次々に机の下に入れ替える、朝の儀式が始まった。
「うわ~~~~!!!」
という大きな声と共に、イスがひっくり返る音がした。タカヒロだ。
「おい!誰だよ!オレの机にバナナ入れたの!?」
僕は「クックックック・・・」と堪えた笑いを漏らす。
タカヒロはそのバナナを掴むこともできず、しばらく机の周りをウロウロしていた。
こっちは笑いをこらえるのに必死だった。
その日から僕は次々とあの手この手でバナナ攻撃を喰らわせてやった。
バナナを体操着袋の中に入れたり、下駄箱の上履きに突っ込んでやったり、縦笛の袋の中身をバナナにすり替えてやったり。黒板を消すのが日直の役目なので、タカヒロが日直の日に、黒板消しをバナナに替えておいたり。
その度タカヒロは、うわ~!っと大声で叫んだ。
「誰だよ!バナナ入れたやつ!」
すると、そんな元気がなくなったようで、タカヒロはみるみる僕に意地悪をしなくなった。
そして僕は、タカヒロの叫び声を聞くたびに、ずっとからかわれていたことへ仕返し達成感ってやつを感じた。
そんなバナナ攻撃が1か月位続いたある日・・・、
松本先生に頼まれて風邪をひいて学校を休んだタカヒロの家に、連絡帳を届けに行かなければならなくなった。
タカヒロの家は、僕の家から学区内で人気の駄菓子屋を真ん中に挟んで、ほんの3分。
だから、1,2年生の頃はいつも一緒だったんだ。
この駄菓子屋にも毎日のように一緒に行っていた。
そうだ・・・と思い出し、その駄菓子屋に寄って、モロッコヨーグルのバナナ味を買った。
モロッコヨーグルバナナ味を、連絡帳を届けたたついでに、奴の自転車のカゴに入れてやる作戦だ。
きっと、自転車に乗った瞬間に転げ落ちるほどビックリするにちがいない。
大きな白いヨーロピアンな門。
門の向こうにあの上品なお母さんが手入れしているであろうお庭があって、その奥に玄関がある。
絵にかいたようなステキなお家ってやつだ。
僕のママが、タカヒロの家に迎えに来るといつも「いいわね、こんなお庭」とつぶやいていた。
僕はタカヒロのお母さんを三者面談で初めて見たのは、遊びに来るといつもいなかったからだ。
3つ下の妹と一緒にいつもどこかに出かけていた。
門は柵の間から手を突っ込んで開けられることを知っていたので、開けて庭に入った。
玄関のすぐ横にあるリビングの窓が少し空いていてピアノの音が聞こえていた。
なんだかちょっとへたくそな音色だ。へたくそなのに躊躇なく弾いている。
まさか、アイツが弾いてるのか?そう思ってリビングの端の窓から中をちょっとだけ覗いてみた。
タカヒロはリビングのソファに座って泣いていた。
ポロポロ、ポロポロと大粒の涙をこぼして。
つまりピアノを弾いているのはタカヒロじゃなかった。
あの上品なお母さんが駆け寄ってきた。
「タカヒロ、どうしたの?」
ピアノの音が止まった。
「なんでもない!」
ピアノの音が止まって、リビングに入ってきたのは、とっても小さな女の子だ、髪の毛は肩ぐらい。女の子なら誰もがうらやましがりそうな薄いピンクのワンピースを着て、タカヒロの膝にちょこんと座った。
「オニイチャン、ナカナイデ」
たどたどしい言葉だった。
「ミヨ、ごめんな。俺のせいで。」
少し間を空けてから、妹のミヨはタカヒロに抱き着いた。
「オニイチャンノ セイジャナイ」
やっぱりたどたどしい言葉だった。
その時、僕は気が付いた。ミヨは耳が聞こえないんだ。
一生懸命タカヒロの口元を見て、会話をしていた。
「アナタのせいじゃないわよ、タカヒロ。3年前の春休みだったわね。アナタとミヨが一緒に散歩していて、たまたまバナナの皮が落ちていただけなのよ。それをミヨが踏んでしまったのは、本当にたまたま。アナタが守ってあげられなかったんじゃないわよ。」
「でも・・・僕はお兄ちゃんなのに・・・僕が踏めばよかったのに・・・」
大粒の涙は、涙製造工場のようにポタポタと落ちている。
ミヨは何度も何度も首を横に振った。
「頭を打ったショックで耳が聞こえなくなってしまったけど、ミヨはこうして元気よ。お兄ちゃんの優しさを人一倍感じて育ってくれてるの。アナタのおかげよ。」
ミヨは何度も首を縦に振った。
「オニイチャン、ダイスキ」
3年生になる春休みに起きた出来事だったんだ。
僕をからかうようになったのは、3年生の春からだった。
そうだったんだ。僕は初めてそれを知った。
きっと、タカヒロは悲しい気持ちを僕にぶつけてたんだ。
そして、僕はバナナが大嫌いな理由を知ってしまった。
連絡帳を玄関の前にそっと置いて、モロッコヨーグルのバナナ味を握りしめたまま走って家に帰った。
できるだけ早く走って。
続く→→
僕は、いつもより30分も早く教室についた。
僕の反撃開始の記念すべき日だからだ。
準備OK、僕は今日から最強になれる!僕にはヤツがいる!
クラスのみんなが教室に着き始め、ランドセルから筆記用具、教科書、ノート・・・と次々に机の下に入れ替える、朝の儀式が始まった。
「うわ~~~~!!!」
という大きな声と共に、イスがひっくり返る音がした。タカヒロだ。
「おい!誰だよ!オレの机にバナナ入れたの!?」
僕は「クックックック・・・」と堪えた笑いを漏らす。
タカヒロはそのバナナを掴むこともできず、しばらく机の周りをウロウロしていた。
こっちは笑いをこらえるのに必死だった。
その日から僕は次々とあの手この手でバナナ攻撃を喰らわせてやった。
バナナを体操着袋の中に入れたり、下駄箱の上履きに突っ込んでやったり、縦笛の袋の中身をバナナにすり替えてやったり。黒板を消すのが日直の役目なので、タカヒロが日直の日に、黒板消しをバナナに替えておいたり。
その度タカヒロは、うわ~!っと大声で叫んだ。
「誰だよ!バナナ入れたやつ!」
すると、そんな元気がなくなったようで、タカヒロはみるみる僕に意地悪をしなくなった。
そして僕は、タカヒロの叫び声を聞くたびに、ずっとからかわれていたことへ仕返し達成感ってやつを感じた。
そんなバナナ攻撃が1か月位続いたある日・・・、
松本先生に頼まれて風邪をひいて学校を休んだタカヒロの家に、連絡帳を届けに行かなければならなくなった。
タカヒロの家は、僕の家から学区内で人気の駄菓子屋を真ん中に挟んで、ほんの3分。
だから、1,2年生の頃はいつも一緒だったんだ。
この駄菓子屋にも毎日のように一緒に行っていた。
そうだ・・・と思い出し、その駄菓子屋に寄って、モロッコヨーグルのバナナ味を買った。
モロッコヨーグルバナナ味を、連絡帳を届けたたついでに、奴の自転車のカゴに入れてやる作戦だ。
きっと、自転車に乗った瞬間に転げ落ちるほどビックリするにちがいない。
大きな白いヨーロピアンな門。
門の向こうにあの上品なお母さんが手入れしているであろうお庭があって、その奥に玄関がある。
絵にかいたようなステキなお家ってやつだ。
僕のママが、タカヒロの家に迎えに来るといつも「いいわね、こんなお庭」とつぶやいていた。
僕はタカヒロのお母さんを三者面談で初めて見たのは、遊びに来るといつもいなかったからだ。
3つ下の妹と一緒にいつもどこかに出かけていた。
門は柵の間から手を突っ込んで開けられることを知っていたので、開けて庭に入った。
玄関のすぐ横にあるリビングの窓が少し空いていてピアノの音が聞こえていた。
なんだかちょっとへたくそな音色だ。へたくそなのに躊躇なく弾いている。
まさか、アイツが弾いてるのか?そう思ってリビングの端の窓から中をちょっとだけ覗いてみた。
タカヒロはリビングのソファに座って泣いていた。
ポロポロ、ポロポロと大粒の涙をこぼして。
つまりピアノを弾いているのはタカヒロじゃなかった。
あの上品なお母さんが駆け寄ってきた。
「タカヒロ、どうしたの?」
ピアノの音が止まった。
「なんでもない!」
ピアノの音が止まって、リビングに入ってきたのは、とっても小さな女の子だ、髪の毛は肩ぐらい。女の子なら誰もがうらやましがりそうな薄いピンクのワンピースを着て、タカヒロの膝にちょこんと座った。
「オニイチャン、ナカナイデ」
たどたどしい言葉だった。
「ミヨ、ごめんな。俺のせいで。」
少し間を空けてから、妹のミヨはタカヒロに抱き着いた。
「オニイチャンノ セイジャナイ」
やっぱりたどたどしい言葉だった。
その時、僕は気が付いた。ミヨは耳が聞こえないんだ。
一生懸命タカヒロの口元を見て、会話をしていた。
「アナタのせいじゃないわよ、タカヒロ。3年前の春休みだったわね。アナタとミヨが一緒に散歩していて、たまたまバナナの皮が落ちていただけなのよ。それをミヨが踏んでしまったのは、本当にたまたま。アナタが守ってあげられなかったんじゃないわよ。」
「でも・・・僕はお兄ちゃんなのに・・・僕が踏めばよかったのに・・・」
大粒の涙は、涙製造工場のようにポタポタと落ちている。
ミヨは何度も何度も首を横に振った。
「頭を打ったショックで耳が聞こえなくなってしまったけど、ミヨはこうして元気よ。お兄ちゃんの優しさを人一倍感じて育ってくれてるの。アナタのおかげよ。」
ミヨは何度も首を縦に振った。
「オニイチャン、ダイスキ」
3年生になる春休みに起きた出来事だったんだ。
僕をからかうようになったのは、3年生の春からだった。
そうだったんだ。僕は初めてそれを知った。
きっと、タカヒロは悲しい気持ちを僕にぶつけてたんだ。
そして、僕はバナナが大嫌いな理由を知ってしまった。
連絡帳を玄関の前にそっと置いて、モロッコヨーグルのバナナ味を握りしめたまま走って家に帰った。
できるだけ早く走って。
続く→→